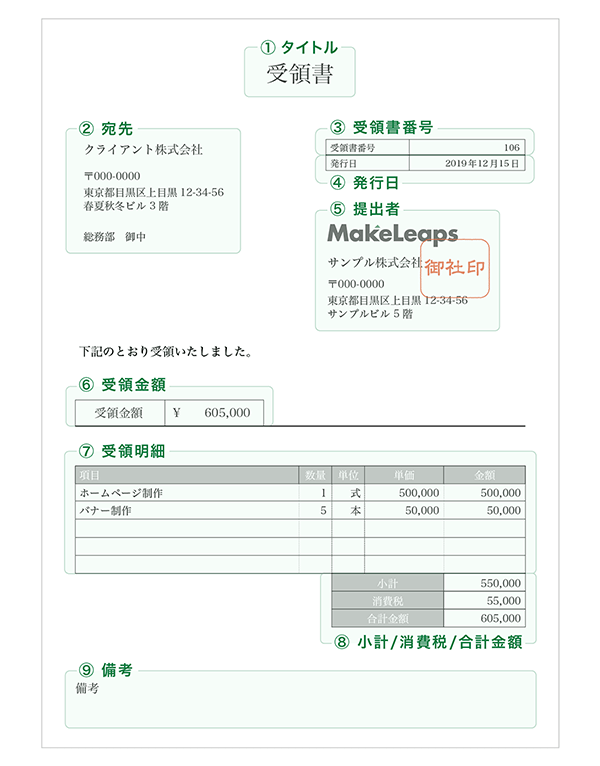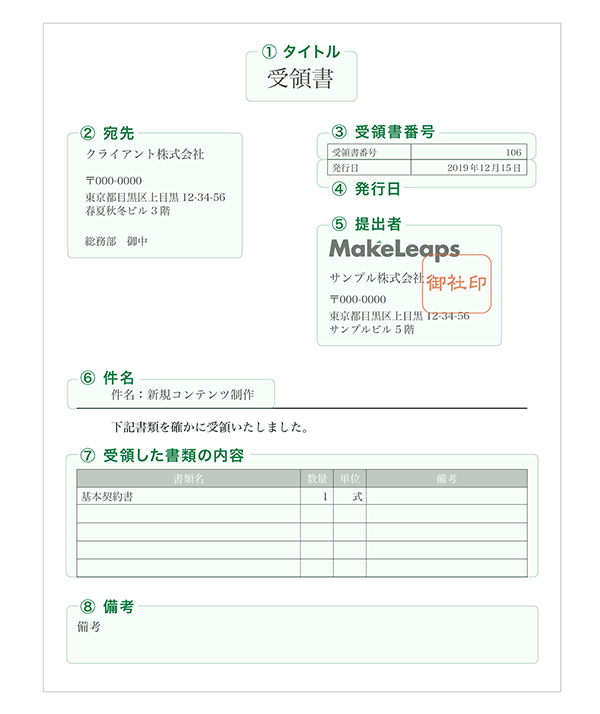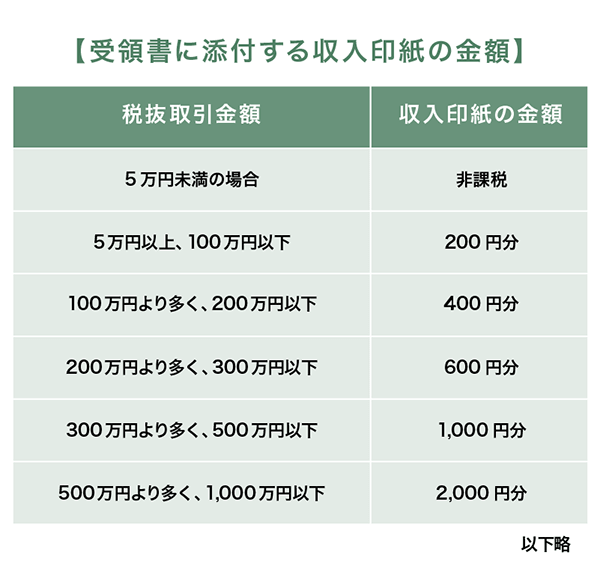受領書エクセルテンプレート・フォーマットの無料ダウンロードページです。
受領書の書き方から発行時の注意点など、説明付きで分かりやすく受領書を作成いただけます。
クラウド見積・請求・入金管理ソフト
MakeLeaps
エクセルテンプレートをそのまま使えます!
「MakeLeaps(メイクリープス)」では、現在使用している書類フォートマットも、新たに作成する場合も、使い慣れたエクセルを使って自由に様々な書類テンプレートのデザインを作成することが可能です。自社のビジネスによりマッチした書類を作成し、クラウドで書類発行のメリットを最大限に活用いただけます。
詳細は、「カスタムテンプレート」機能のページをご確認ください。

この記事でできること
- 受領書のエクセルテンプレートをダウンロードできる!
- 受領書の書き方がわかる!
すぐに使える!受領書エクセルテンプレート/フォーマット無料
テンプレート一覧の中から用途に合うテンプレートを選び、ダウンロードしてご活用ください。
基本用途
-
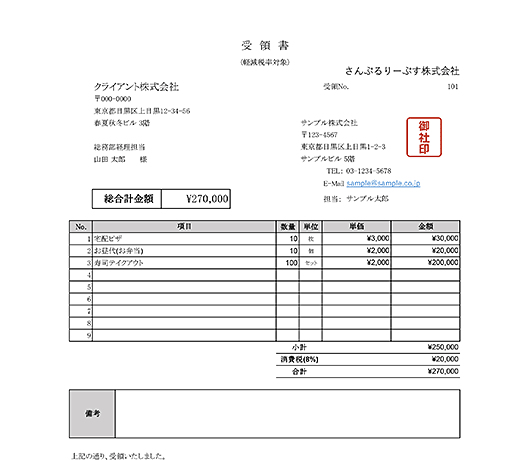
単位あり受領書
Excelテンプレートダウンロード -
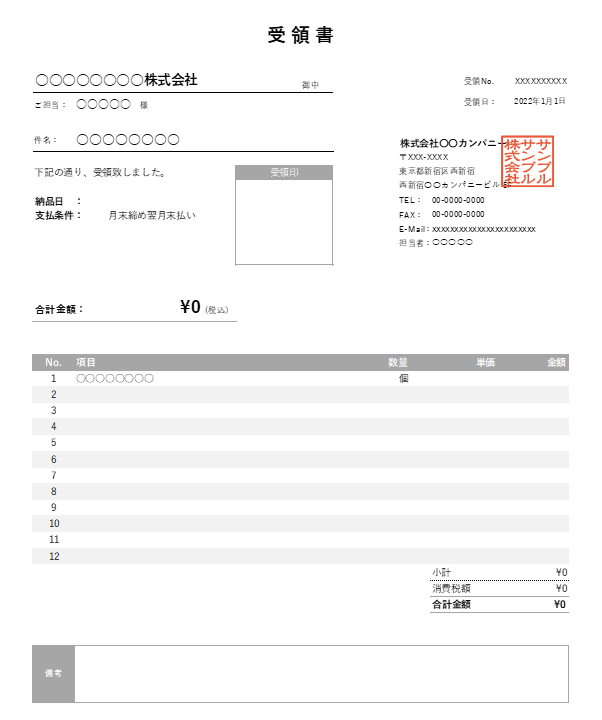
基本の
受領書Excelテンプレートダウンロード -
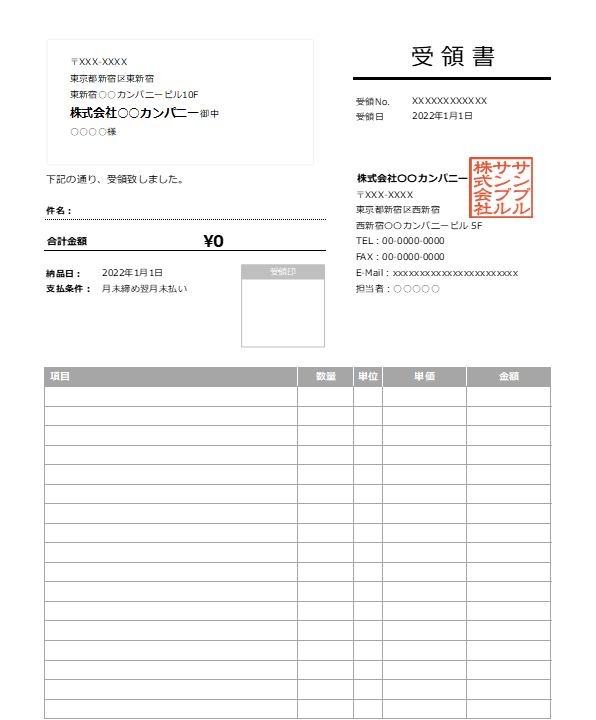
窓付き封筒対応
受領書Excelテンプレート- 窓付対応
ダウンロード -
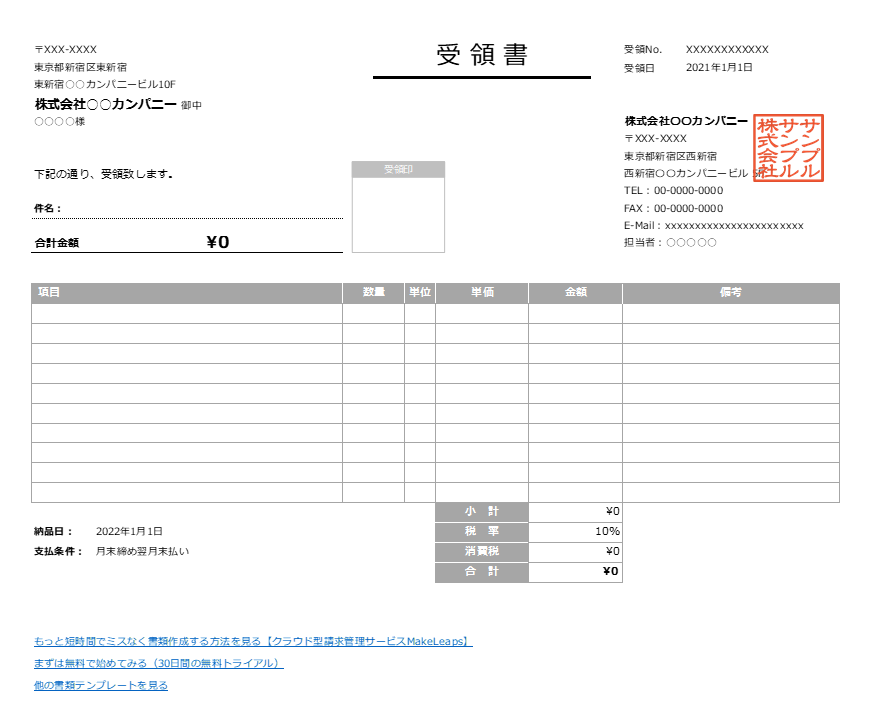
横型の
受領書Excelテンプレートダウンロード -

ブルー・窓付き封筒対応
受領書Excelテンプレート- 窓付対応
- カラーバリエーション
ダウンロード -

ブルー・横型の
受領書Excelテンプレート- カラーバリエーション
ダウンロード -

グリーン・窓付き封筒対応
受領書Excelテンプレート- 窓付対応
- カラーバリエーション
ダウンロード -

グリーン・横型の
受領書Excelテンプレート- カラーバリエーション
ダウンロード -

レッド・窓付き封筒対応
受領書Excelテンプレート- 窓付対応
- カラーバリエーション
ダウンロード -

レッド・横型の
受領書Excelテンプレート- カラーバリエーション
ダウンロード -

オレンジ・窓付き封筒対応
受領書Excelテンプレート- 窓付対応
- カラーバリエーション
ダウンロード
特殊要件
-
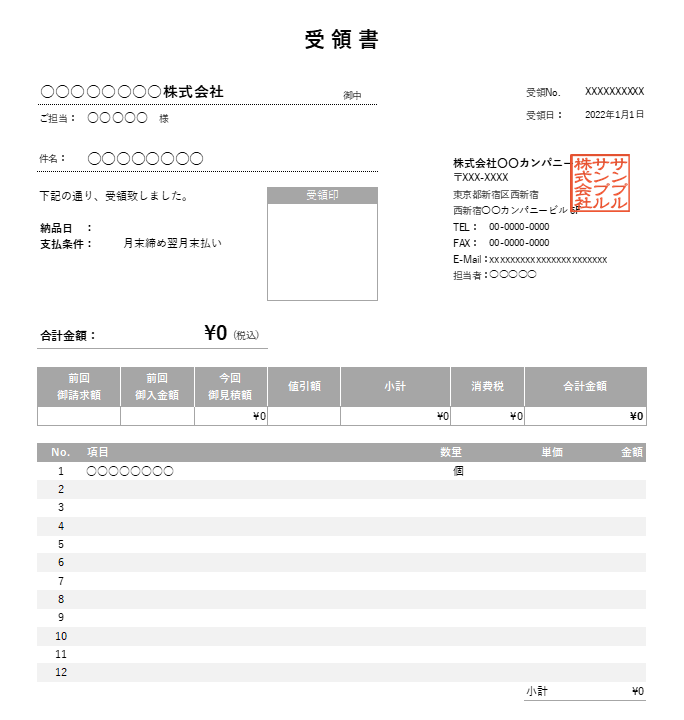
繰越金額・値引き機能付き
受領書Excelテンプレート- 値引
- 繰越計上
ダウンロード -
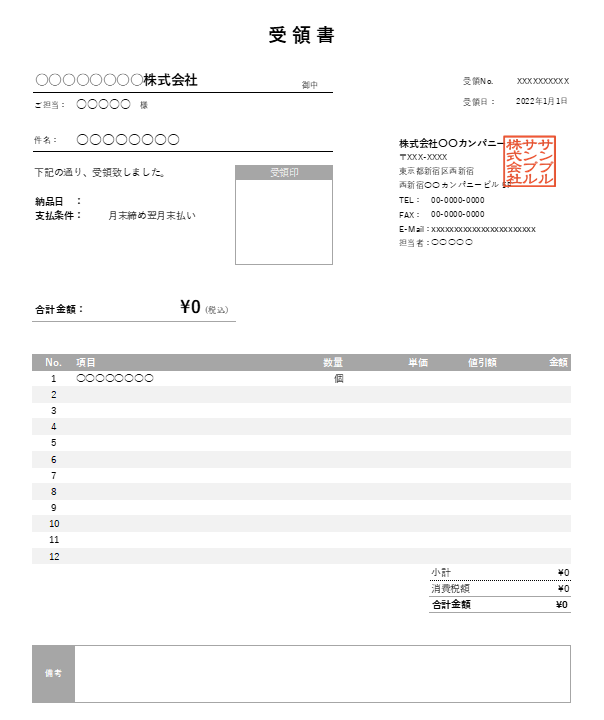
値引き機能付き
受領書Excelテンプレート- 値引
ダウンロード -
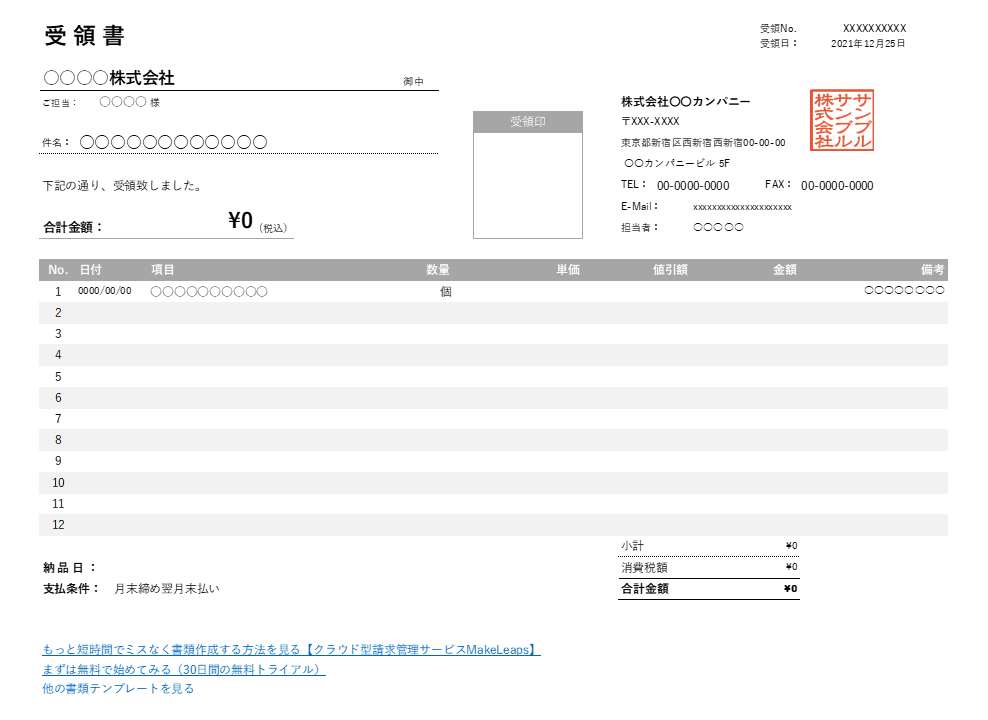
値引き機能付き横型
受領書Excelテンプレート- 値引
ダウンロード -
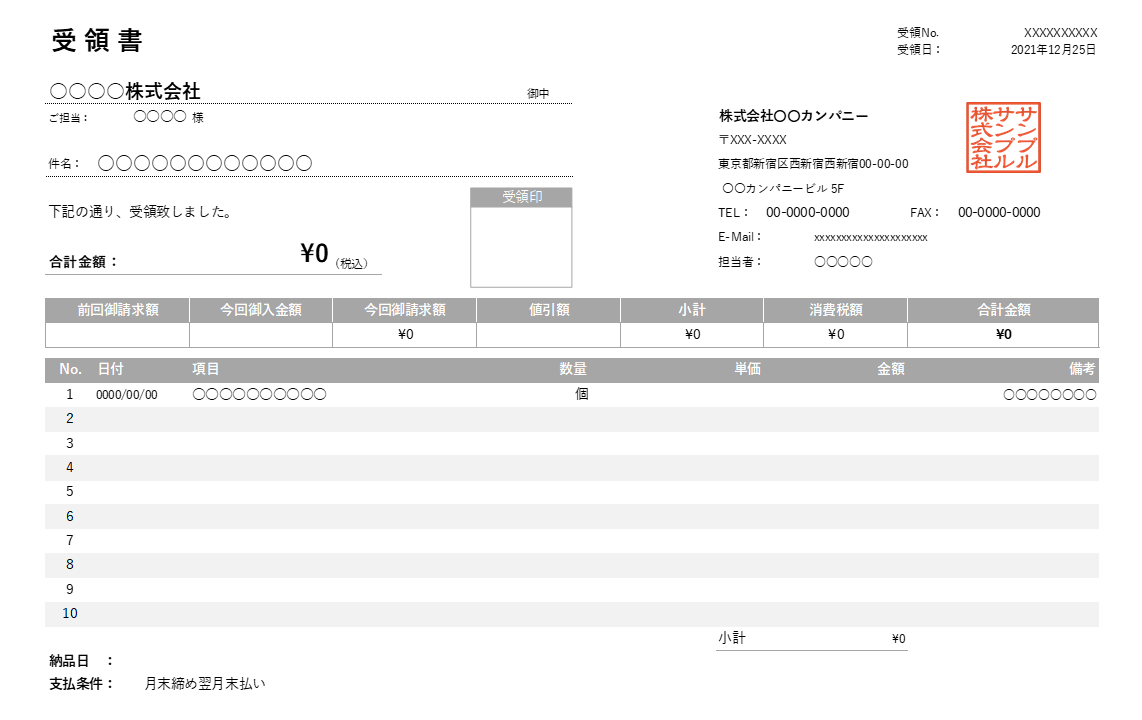
繰越金額・値引き機能付き横型
受領書Excelテンプレート- 値引
- 繰越計上
ダウンロード -
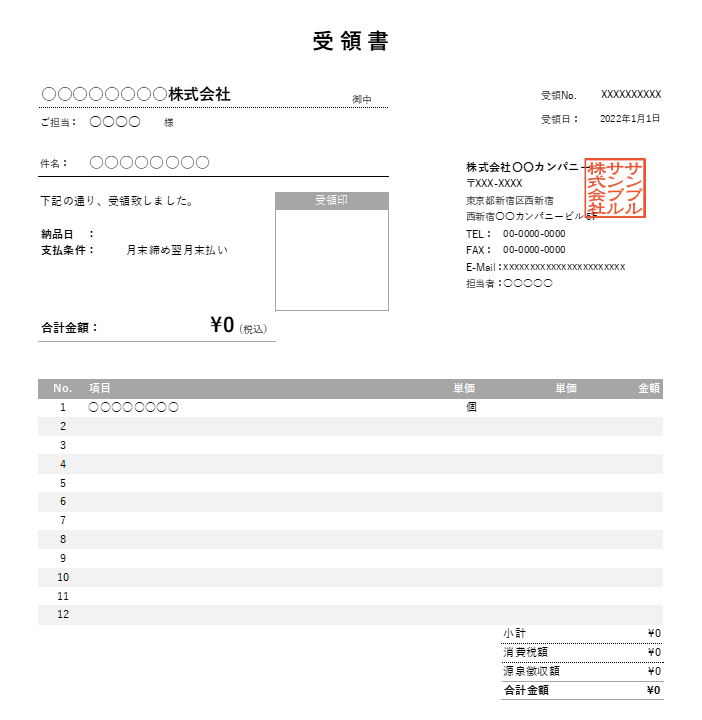
源泉徴収機能付き
受領書Excelテンプレート- 源泉徴収
ダウンロード -
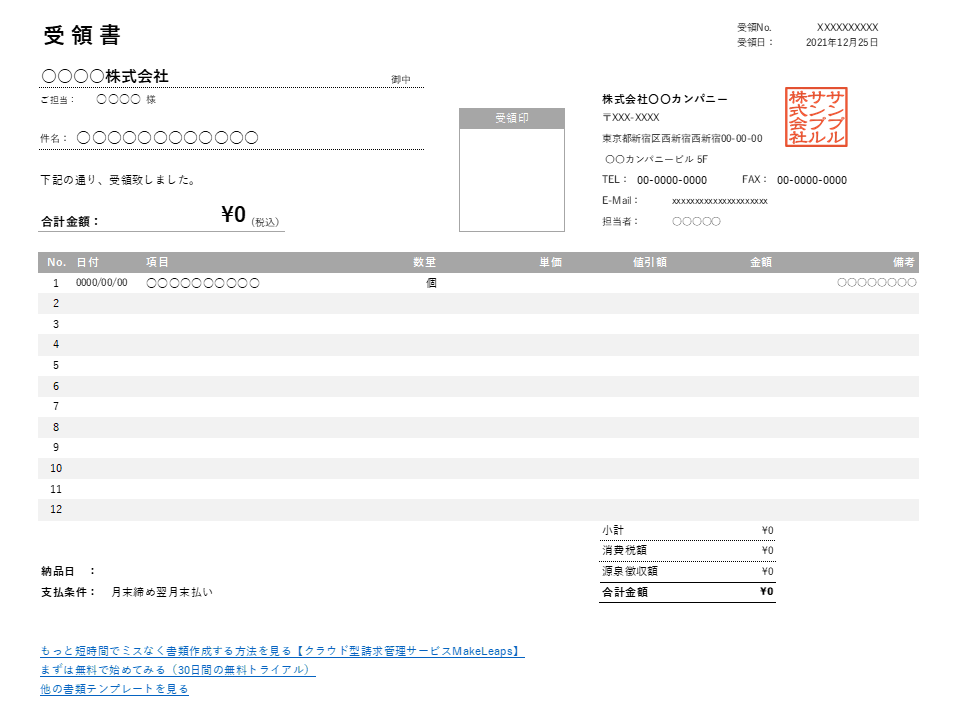
値引き・源泉徴収機能付き横型
受領書Excelテンプレート- 値引
- 源泉徴収
ダウンロード -
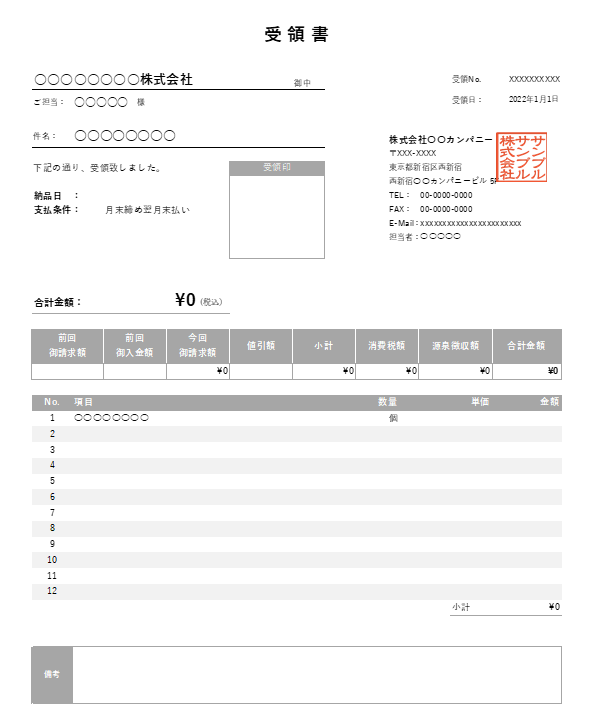
繰越金額・値引き・源泉徴収機能付き
受領書Excelテンプレート- 値引
- 繰越計上
- 源泉徴収
ダウンロード -
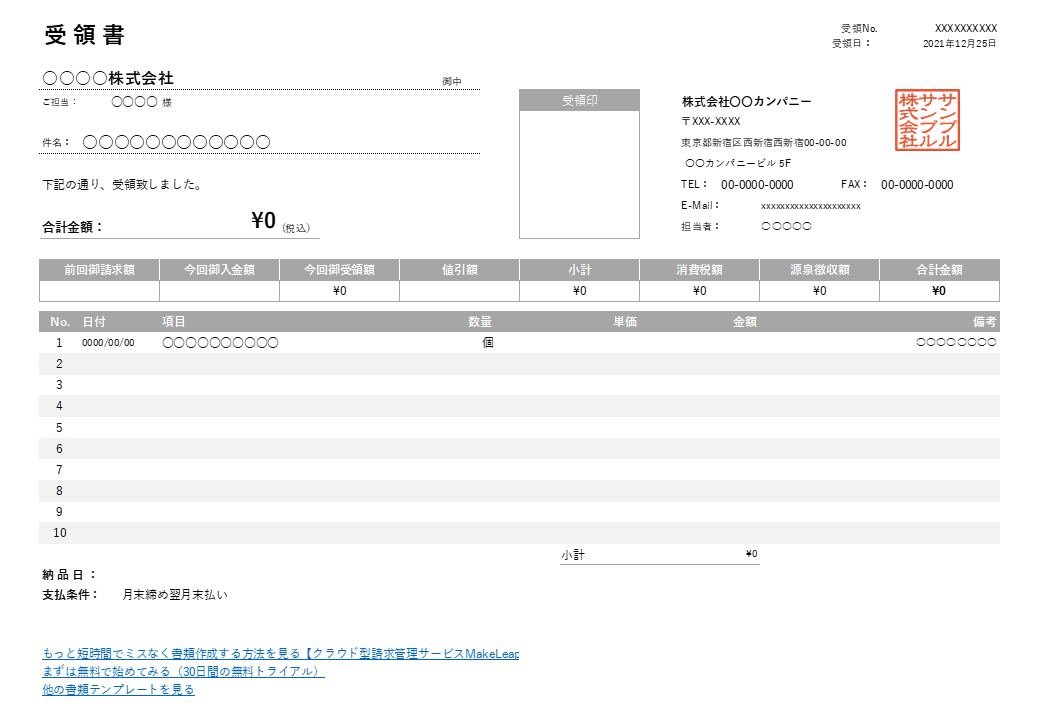
繰越金額・値引き機能付き横型
受領書Excelテンプレート- 値引
- 繰越計上
ダウンロード -
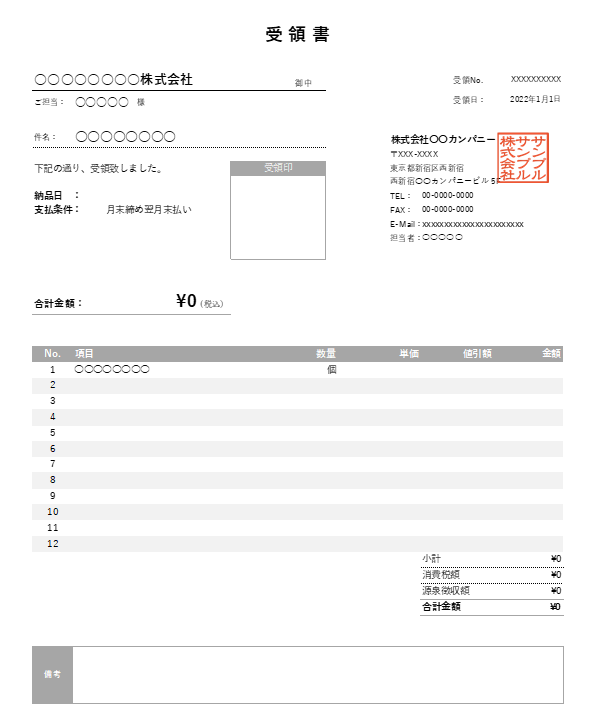
値引き・源泉徴収機能付き
受領書Excelテンプレート- 値引
- 源泉徴収
ダウンロード
軽減税率・混合
英語
-

海外配送用・グリーン・英語
受領書Excelテンプレート- Shipping
- カラーバリエーション
ダウンロード -

オレンジ・横型の
受領書Excelテンプレート- カラーバリエーション
ダウンロード -
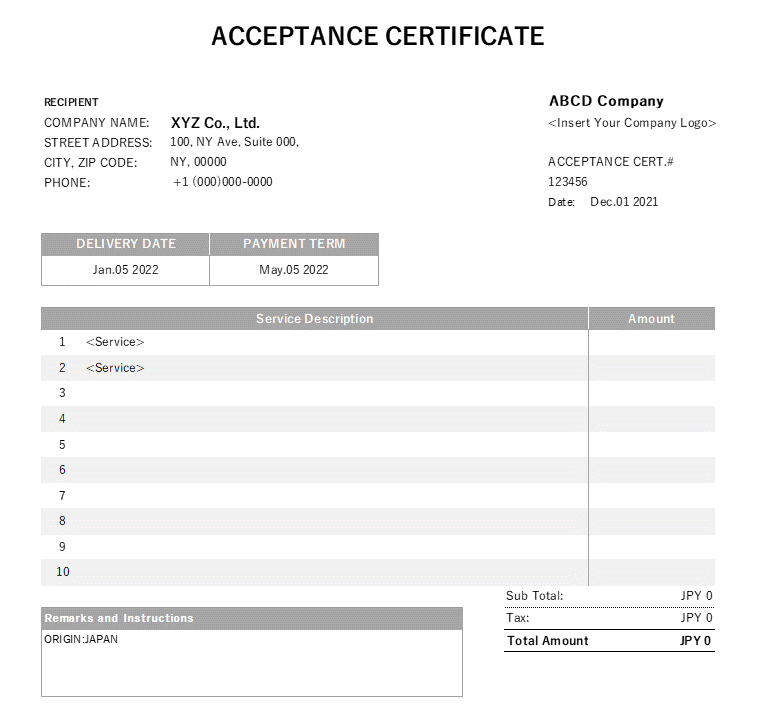
英語の基本的な
受領書Excelテンプレートダウンロード -

製品サイズ入り・英語
受領書Excelテンプレート- 製品サイズ
ダウンロード -

製品サイズ・アイテムコード入り・英語
受領書Excelテンプレート- 製品サイズ
- アイテムコード
ダウンロード -

英語(ブルー)の基本的な
受領書Excelテンプレート- カラーバリエーション
ダウンロード -
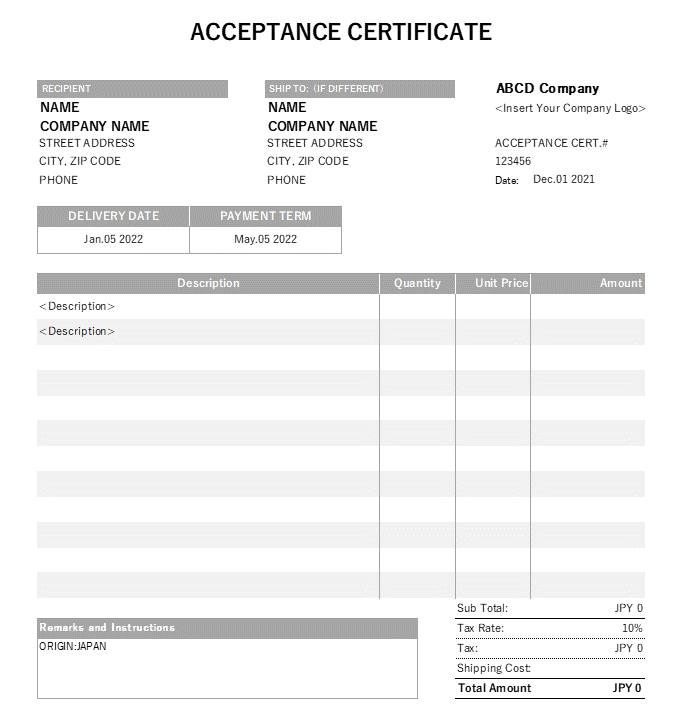
海外配送用・英語
受領書Excelテンプレート- Shipping
ダウンロード -

製品サイズ入り・ブルー・英語
受領書Excelテンプレート- 製品サイズ
- カラーバリエーション
ダウンロード -

製品サイズ・アイテムコード入り・海外配送用・ブルー・英語
受領書Excelテンプレート- 製品サイズ
- アイテムコード
- Shipping
- カラーバリエーション
ダウンロード -
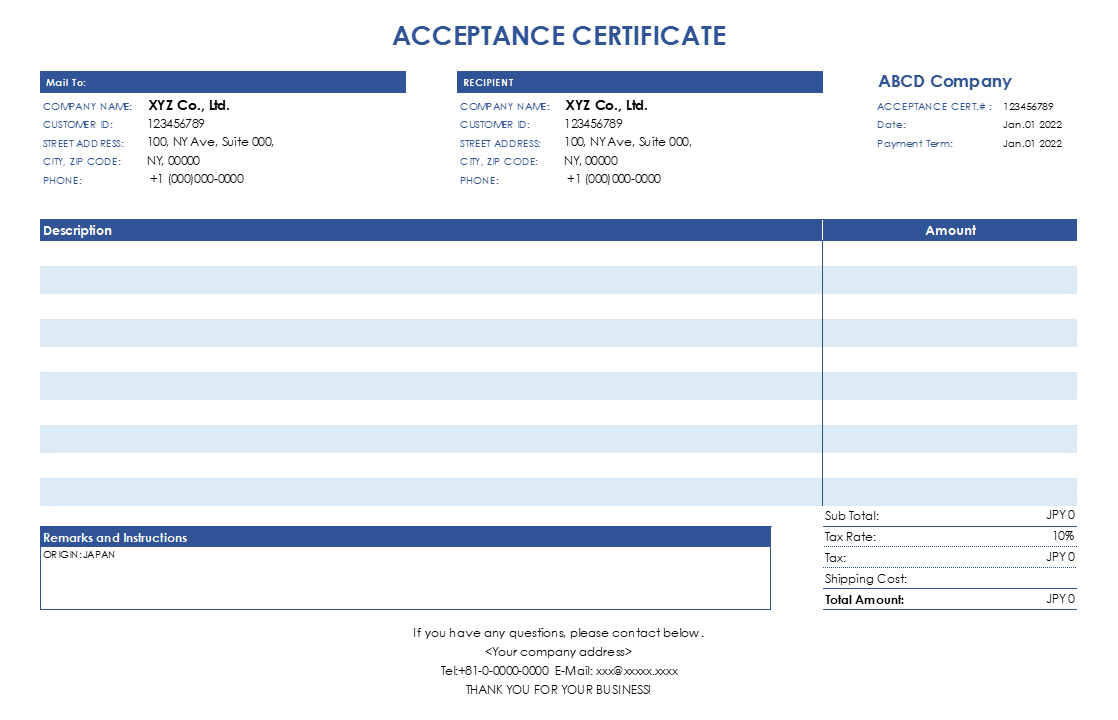
海外配送用・ブルー・英語
受領書Excelテンプレート- Shipping
- カラーバリエーション
ダウンロード -

製品サイズ・アイテムコード入り・海外配送用・英語
受領書Excelテンプレート- 製品サイズ
- アイテムコード
- Shipping
ダウンロード -
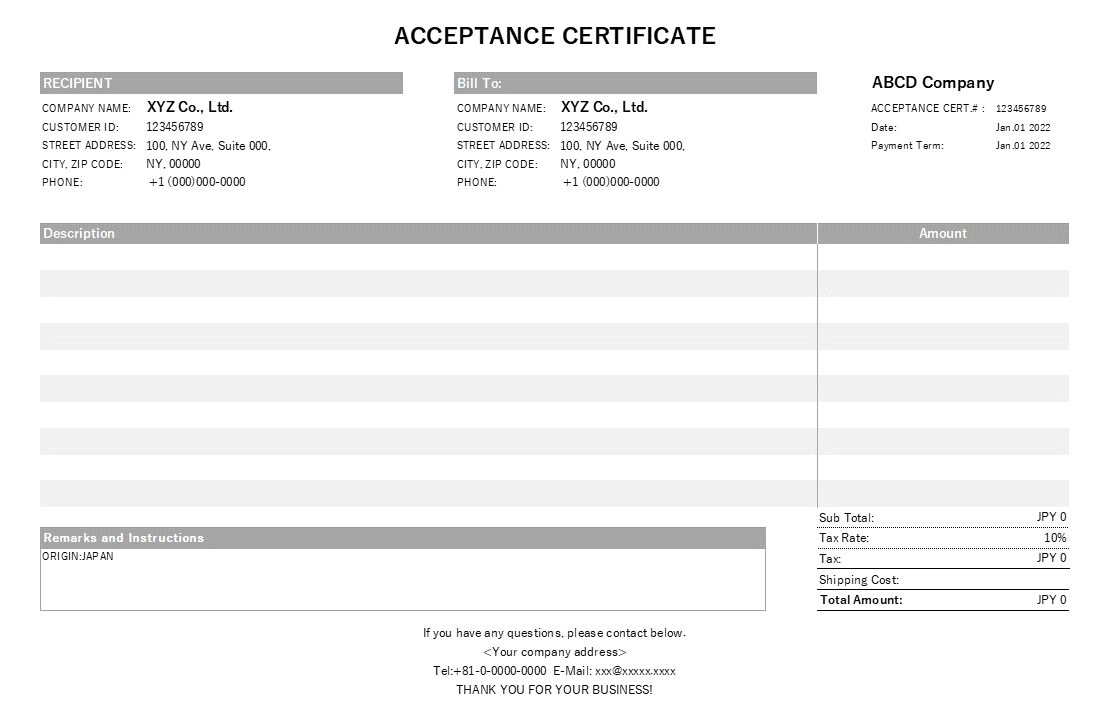
海外配送用・英語
受領書Excelテンプレート- Shipping
ダウンロード -

製品サイズ入り・レッド・英語
受領書Excelテンプレート- 製品サイズ
- カラーバリエーション
ダウンロード -

海外配送用・レッド・英語
受領書Excelテンプレート- カラーバリエーション
- Shipping
ダウンロード